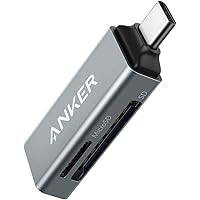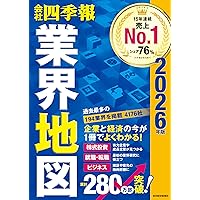『悪法も法なり』は本当にソクラテスの言葉か?
この有名な格言の真偽を、プラトンの『クリトン』やソクラテスの実際の思想から検証してみましょう。
「悪法も法なり」という言葉は、日本では非常に有名な格言として知られており、多くの人がソクラテスの言葉だと信じています。しかし、実際にプラトンが記録した『クリトン』を詳しく読んでみると、ソクラテスがこの通りの言葉を発したという記述は見当たりません。むしろ、ソクラテスは法の重要性について語りながらも、より複雑で微妙な議論を展開しているのです。
プラトンの『クリトン』では、死刑判決を受けたソクラテスが友人クリトンから脱獄を勧められる場面が描かれています。この対話の中で、ソクラテスは確かに法に従うことの重要性を説いていますが、それは単純に「悪法でも従うべきだ」という主張ではありませんでした。彼は国家との約束や契約の観点から、また自分の哲学的信念との一貫性を保つ観点から、刑の執行を受け入れることを選択したのです。
この誤解が生まれた背景には、後世の人々がソクラテスの複雑な思想を単純化し、わかりやすい格言として伝承してきたことがあります。特に日本では、明治時代以降の西洋哲学の受容過程で、このような簡潔な表現が好まれ、教育現場でも広く使われるようになりました。しかし、これはソクラテス本来の思想の豊かさを見失う危険性をはらんでいるのです。
日本での普及過程と、西洋哲学における法と正義の関係についてソクラテスが本当に語ったことを探ります。
「悪法も法なり」という表現が日本で広まったのは、明治時代の西洋哲学導入期にさかのぼります。当時の知識人たちは、複雑な西洋の哲学思想を日本語で表現する際に、理解しやすい格言形式を好む傾向がありました。ソクラテスの法に対する態度も、この過程で単純化され、「悪法も法なり」という短い言葉に集約されてしまったのです。この表現は戦後の道徳教育や法学教育でも頻繁に使われ、日本人の法意識形成に大きな影響を与えました。
実際のソクラテスが『クリトン』で展開した議論は、はるかに洗練されたものでした。彼は法の権威について語る際、国家との関係を親子関係や師弟関係になぞらえ、一方的な服従ではなく、相互の約束に基づく関係として捉えていました。ソクラテスによれば、市民は国家の法に従う義務がありますが、それは盲目的な服従ではなく、長年にわたって国家の恩恵を受け、その法体系の下で生活してきたことに対する道義的責任なのです。
さらに重要なのは、ソクラテスが正義と法の関係について持っていた独特の視点です。彼は生涯を通じて「無知の知」を説き、既存の価値観や制度に対して絶えず疑問を投げかけ続けました。法についても例外ではなく、法が正しいかどうかを常に吟味する姿勢を貫いていました。彼が最終的に死刑を受け入れたのは、法への盲従ではなく、自分の哲学的信念を最後まで貫き通すための選択だったのです。この複雑で深遠な思想を「悪法も法なり」という単純な格言で表現することは、ソクラテスの真意を大きく歪めることになりかねません。